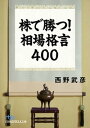【証券用語】相場格言「節分天井、彼岸底」とは?意味を解説!

nekoji
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
この記事では、相場格言「節分天井、彼岸底」の意味と、株式投資への活かし方を解説します。
相場格言を知って学ぶことで、実際の株式投資で起こる様々な状況に対応できるようになりましょう!
格言の由来・読み方
「節分天井、彼岸底(せつぶんてんじょう、ひがんぞこ)は、日本で生まれた相場格言です。
昔の相場から使われてきた言葉です。
格言の意味
年初から新春相場が始まると、節分の時期である2月上旬に株価がピークをむかえて高値をつけることが多くあります。
しかし、企業の決算が集中する彼岸の3月下旬ころに決算対策のため調整局面になり、しだいに下落して安値になるという風に昔から言い伝えられています。
そのため、株価は2月3日の節分の頃に天井をつけて、3月20日前後の彼岸の頃に底をつけることが多いという意味です。
格言から学べること
過去の経験則として、節分の時期に高値をつけて、彼岸の時期に安値をつけやすいということが言われています。
年初の取引から、新春相場で株価が上昇し、節分の時期には株価が高くなっていきます。
その後は3月にある決算期が近づき、企業が利益を出すために株を売ることが多いため、彼岸の時期に向かって株価が下落していき、底をつけると言われています。
あくまでも過去の経験則に基づく格言だから、信用しすぎてもダメだよ。

結局はちゃんと自分で判断しろってことだね。

まとめ
一般的に節分で高値をつけ、彼岸で安値をつけるとされています。
必ず当てはまるわけではないので、当てはまるのかを考えてから売買しましょう。
最後に今回の内容をまとめておきます。
簡潔に言うと…
- 新春相場で株価が上がる
- 節分の頃に高値をつける
- 彼岸には企業が株を売るので、株価が底をつける